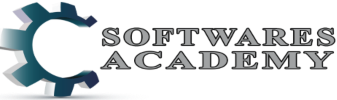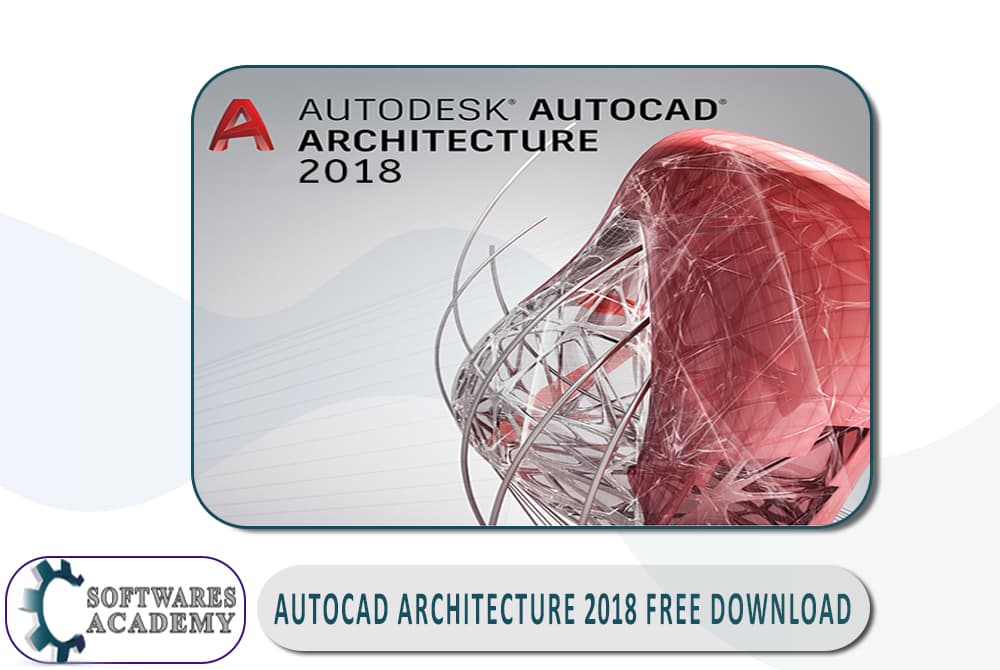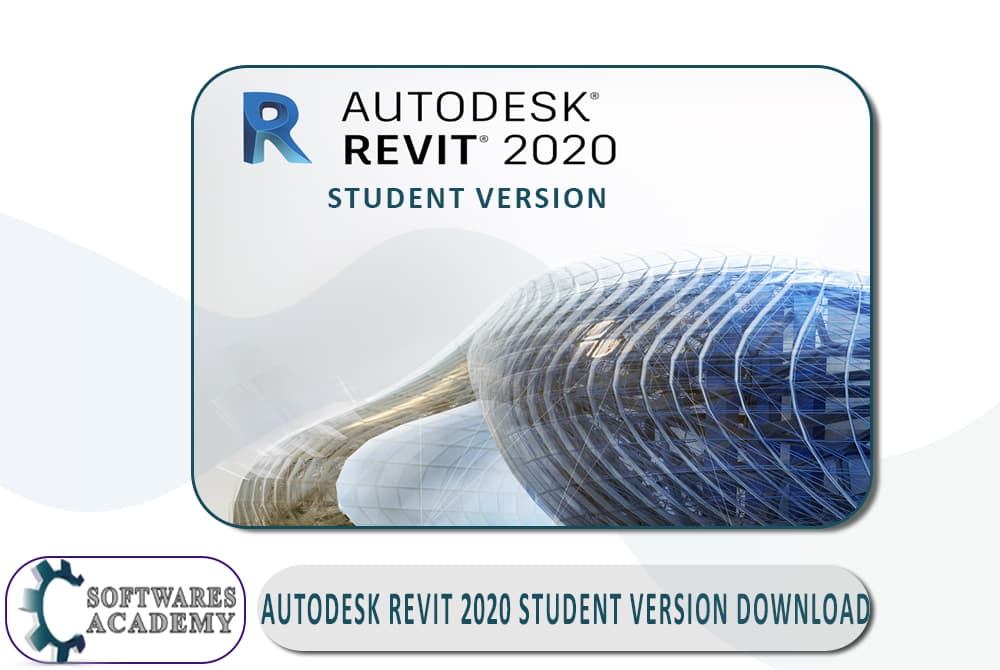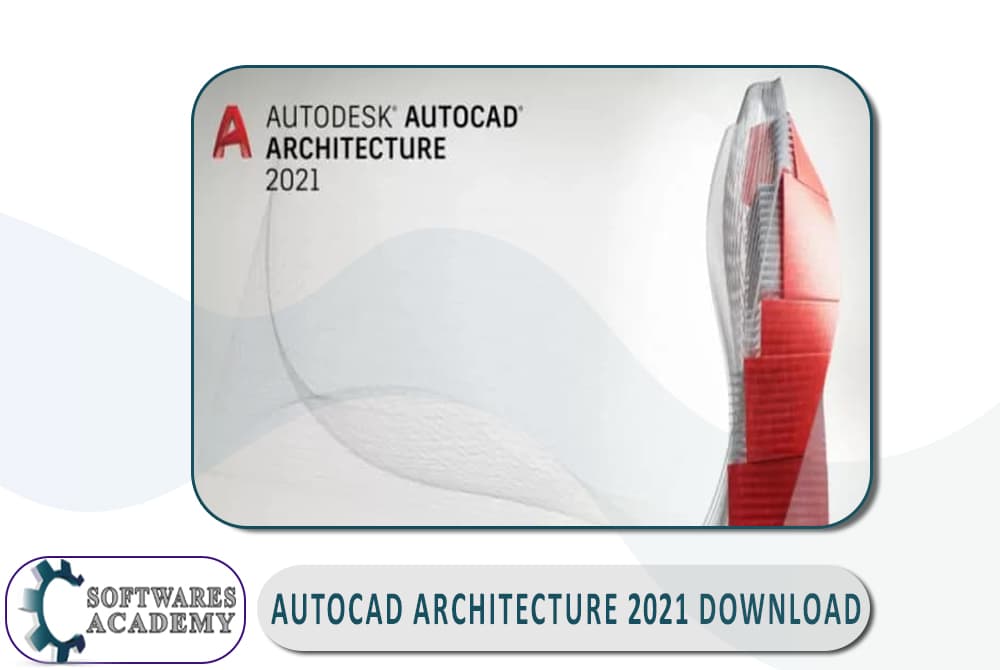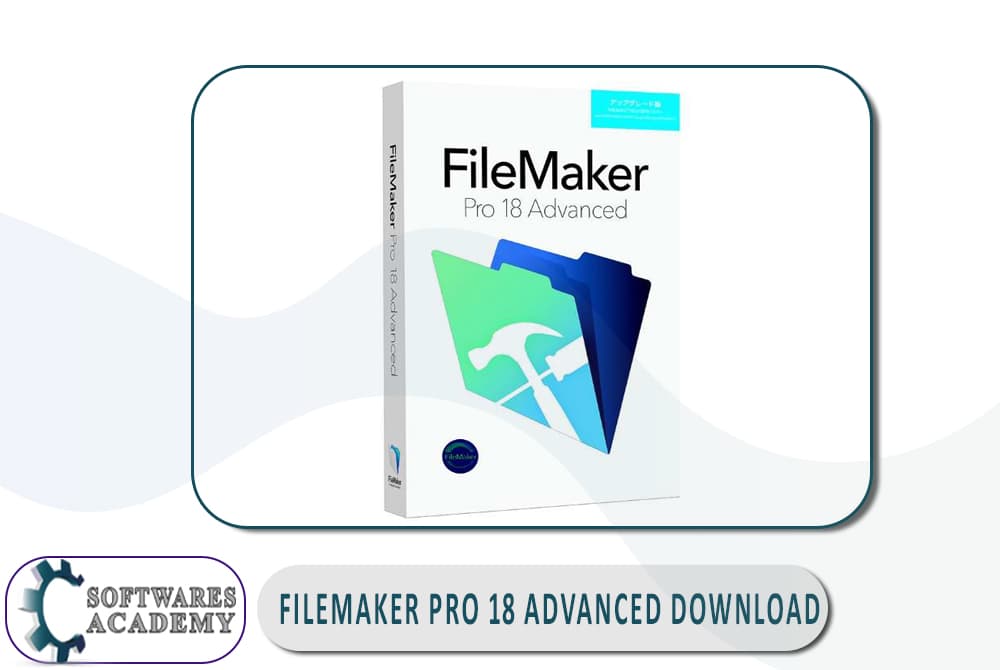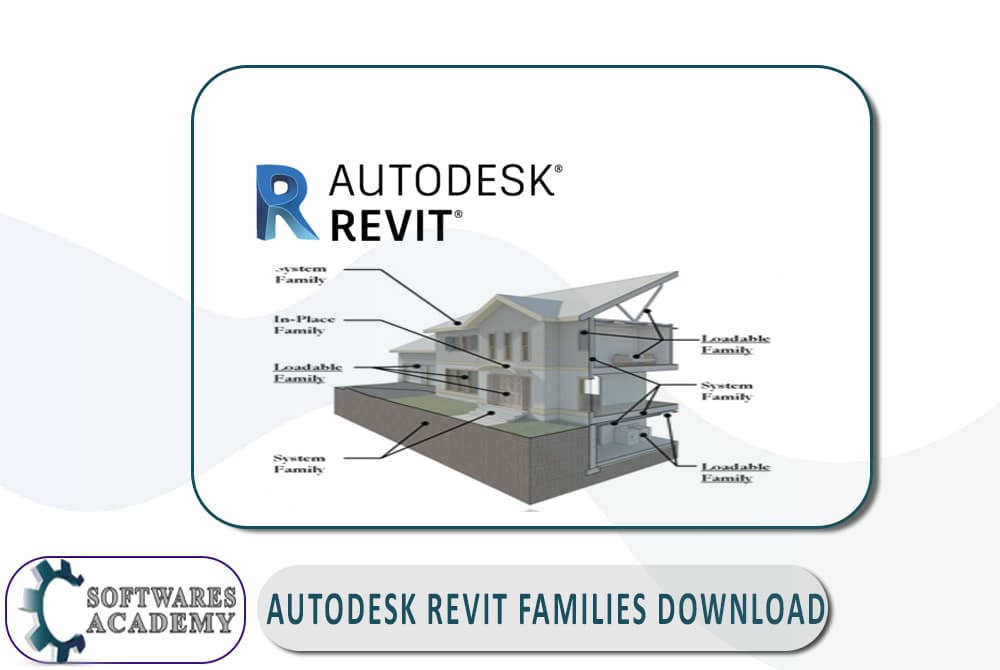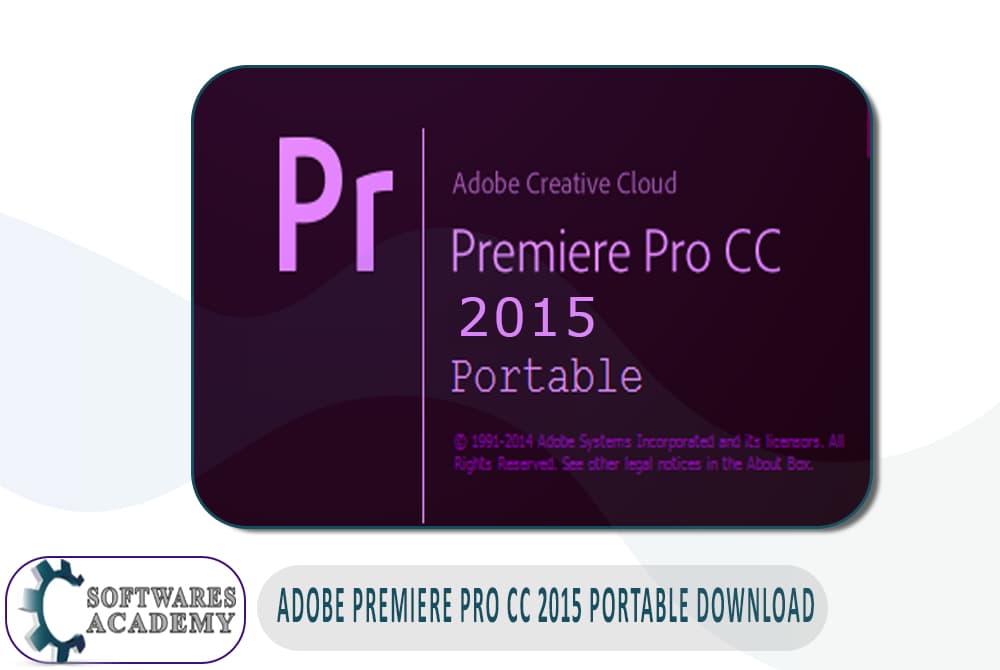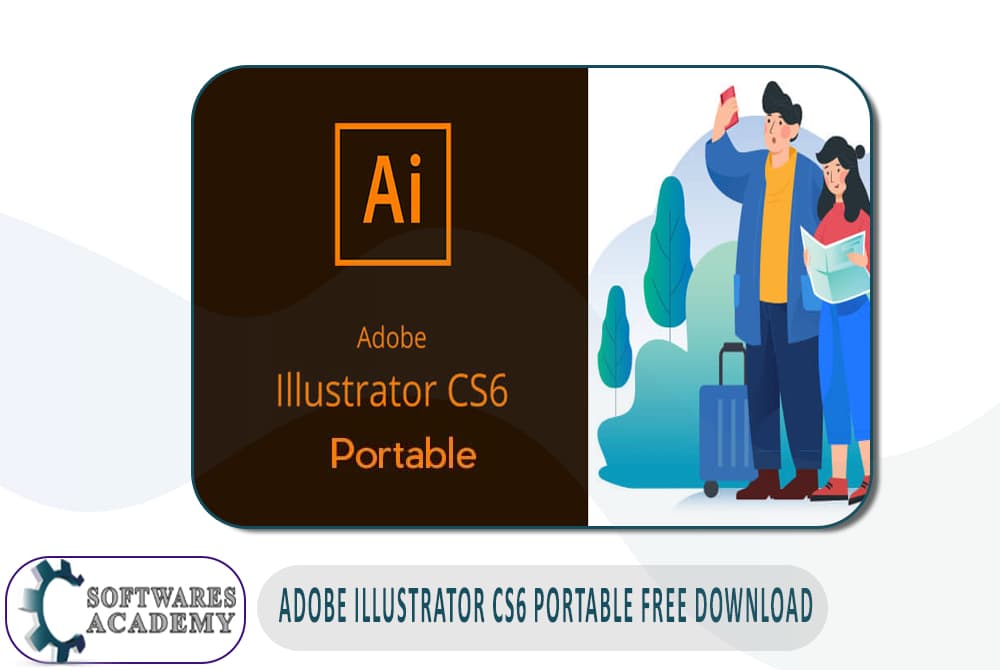AutoCAD Architecture 2018 Free Download
AutoCAD Architecture 2018 Free Download is a highly advanced architectural and design software developed by Autodesk. It stands as one of Autodesk’s most popular products, catering specifically to architects who use AutoCAD. This software offers a unique blend of 2D drawing capabilities alongside real-time 3D architectural design. It facilitates high-quality and efficient CAD work while … Read more